建物探訪
後楽園内にある建造物のご紹介
園内各所に配された延養亭をはじめ能舞台や茶室などの建物には、当時の歴代藩主のさまざまな思いが込められています。
また各建物はお客様に貸出をしています。(有料、予約制。延養亭を除く)
庭園を眺めながらのお茶会やお食事会、そしてお花見などにいかがでしょうか。詳しくは、建物貸出のご案内をご覧下さい。
(1)延養亭(えんようてい)

藩主が後楽園を訪れた時の居間として使われた建物です。築庭当初から現在の位置に建てられ、藩主の座る主室からの眺めが最も美しくなるように、庭園が作られています。戦災で焼失したが、昭和35年、築庭当時の後楽園を描いた「御茶屋御絵図」を元に、当時第一級の材料を集め、最高の技術によって復元されました。
(2)鶴鳴館(かくめいかん)

江戸時代から伝わっていた建物は戦災で焼失し、その後昭和24年、山口県岩国市の吉川邸を移築したもので、武家屋敷のたたずまいをよく伝えるものです。 江戸時代にあったのは茅葺きの建物で、数室に分かれ、使う人の格や用途に応じて使われていました。時には来訪者をもてなす部屋としても使われました。
(3)鶴鳴館本館(かくめいかんほんかん)

昭和25年山口県岩国市の吉川邸を移築したものです。
(4)能舞台(のうぶたい)

後楽園の築庭を命じた綱政は、能に熱心で優れた舞手でもあり、時には藩内の人々に拝見を許しました。 能舞台も戦争で焼失したため、綱政の子、継政時代の遺構をもとに復元されました。 鏡板の松と切戸口板壁の竹の絵は、郷土の画家池田遙邨画伯の筆によるものです。
(5)栄唱の間(えいしょうのま)

能舞台正面にあり、能の見所(けんしょ)となっています。 南側は花葉の池などの眺めに優れています。
(6)墨流しの間(すみながしのま)

能舞台脇正面にあり、東側の障子をはずすと能の脇見所(けんしょ)となります。床(とこ)の壁に、墨を流したような壁紙を張っていたため「墨流しの間」と呼ばれています。
(7)方竹の間(ほうちくのま)

栄唱の間の西側に続いてある茶室で、床柱に四方竹(四角い竹)が使われているため「方竹の間」と呼ばれています。
(8)廉池軒(れんちけん)

園内に点在する亭舎の中で、築庭を指示した藩主池田綱政がもっとも好んで利用していたといわれています。 廉池軒からの眺望は水の景色に優れています。
(9)観騎亭(かんきてい)

園内北に位置する馬場に面して建っています。 江戸時代には、家臣が馬術の上達ぶりを藩主の前で披露する行事があり、藩主は、この建物からその様子を眺めました。 桜の時期には、180メートルの馬場を桜が染め、花見の人気スポットとなります。
(10)新殿(しんでん)

文久3年(1863年)の絵図には、「新御殿」と記されています。 高床式構造の建物のため、少し高い目線で茶畑越しに園内の西側を眺めることができます。
(11)寒翠細響軒(かんすいさいきょうけん)

沢の池をぐるりと臨むことのできる美しく小さな建物。 寒翠はさえた緑色、細響は細やかな響きという意味。背後の松の緑と沢の池の清らかな水の趣がその名前になっているといわれています。 南側の障子を開けると、正面に唯心山や沢の池が一望できます。
(12)茶祖堂(ちゃそどう)

幕末の家老の下屋敷にあった利休堂が、明治20年頃に移築されました。 戦後再建され、岡山の生まれで「茶」を日本に伝えた栄西禅師も一緒にまつられたことから「茶祖堂」と呼ばれるようになりました。
(13)茂松庵(もしょうあん)

戦災で焼け、昭和27年秋再建されました。 二色が岡にあり、落ち着いた佇まいとなっています。 お茶席としての使用に限り、借りることができます。
(14)島茶屋(しまぢゃや)

園内最大の池である「沢の池」の中の島にある茶屋です。
この記事に関するお問い合わせ先
岡山後楽園
〒703-8257
岡山市北区後楽園1-5
電話番号:086-272-1148
ファックス:086-272-1147







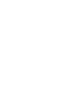
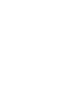

更新日:2024年04月01日